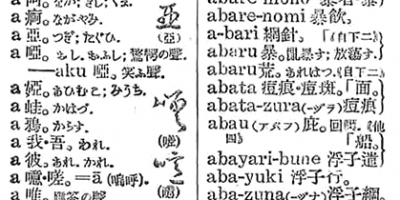前回,食卓ではおいしいとしか言えないことを確認しました。私たちのからだの構造に理由づけられているため,その事情は英語でも変わりません。ただ,英語で「おいしい」に対応するはずのdeliciousということばは,さほど使用頻度が高いわけではなく,その代わりniceとかlovelyとかいった一般的な評価語で表現されることが多いようです。また,mmm(「うーん」もしくは「ふ〜む」くらいか)といったことばにならない反応も,食卓の会話にしばしば現れます。1)
(41) Simon: _ mm_mm: (0.2) that’s _lovely(フム〜,いいね) (Wiggins論文,321ページ)
括弧内の数字は,ポーズの秒数を表します。このmmmは,話者が食べ物をまさに今味わっており,その味わいが心地よいことを示します。口のなかがいっぱいで,すぐには発話できないときの合図にもなります。
明瞭な語彙ではないmmmによって味覚の評価を伝えるのには,それなりの理由があります。味覚はやはり言語化しがたいのです。実際,あまりにおいしいものを食べたときは,「おいしい」ということばすら奪われてしまいます。うっとりと目を閉じて,美味の感覚に身を任せることって,ないですか。おいしさは私たちを寡黙にするのです。
とすると,味覚がことばになりにくいのは,生理上の裏付けがあるはずです。そういう情報を探していたら,友人から解剖学者,養老孟司の対談集の存在を知らされました。養老は嗅覚とことばの関係について次のように述べます。
においという感覚がとらえにくいのは、脳の構造と関係があると私は思っています。嗅球から伸びた神経は、二つに分かれて、一方は大脳の新皮質に入るのですが、もう一方は辺縁系に入る。つまり嗅覚の情報の半分は、いわゆる「古い脳」のほうへ行ってしまい、言語機能をもつ新皮質には届かないんです。視覚の場合は、情報がすべて新皮質に入りますから、目で見たものは言葉で表現しやすいのですが、半分しか届かない嗅覚ではそうはいかない。
(日経サイエンス(編)『養老孟司 ガクモンの壁』)
彼は続けて,味覚も情報が半分しか新皮質に入らないと指摘します。つまり,進化過程の早い段階で発達したと考えられる「古い脳」が味覚と嗅覚の認知に大きくかかわり,言語機能を司る新皮質に情報がじゅうぶんに与えられないため,おいしさを分析的に言語化することがむずかしいのです。

これで,味覚表現の不毛に対するなぞがひとつ解けました。現在進行形の味覚経験をことばにしづらいのは,私たちのからだの制約によります。だから,おいしい料理をいただいてもことば巧みにはコメントできず,慣習的で美味の評価として安定した「おいしい」に頼ってしまうのです(ですので,食卓で気の利いたほめことばが思いつかなくとも,自分の表現能力のなさを責めなくてもいいのです。悪い(?)のは人類が共有するこのからだです)。
ですが,もうひとつなぞが残ります。なぜ,食卓では言語化しづらいはずのおいしさが,料理エッセイやネット上のブログで豊かに展開するのでしょうか。
ここからは,解剖学ではなく,言語学(それも談話研究)の領域になります。味覚表現の不毛(おいしいとしか言いようがない)と豊穣(味ことばが豊かである)を分つのは,ことばが生み出される場面──発話のコンテクスト──の違いだからです。味覚表現の不毛は味覚体験まっただ中の食卓の会話で起こるのに対して,味ことばの豊穣は過去の味覚体験を書きことばで表す文章上で生まれるのです。
ならば,このコンテクストの違いに着目してみましょう。おっと,紙数が尽きたようです。続きはまた再来週。
* * *
1)Wiggins, S. “Talking with your mouth full: Gustatory mmms and the embodiment of pleasure.” Research on Language and Social Interaction 35:3, 311-336, 2002.