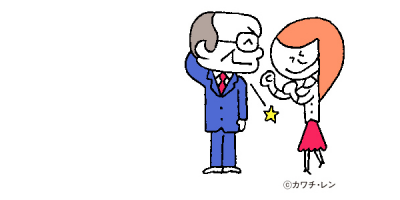五月まつ花橘(はなたちばな)の香(か)をかげば昔の人の袖(そで)の香ぞする
出典
古今・夏・一三九・よみ人しらず / 伊勢・六〇
訳
五月を待って花開く橘の花の香りをかぐと、昔親しんだ人のなつかしい袖の香りがするよ。
注
「香をかげば」の「ば」は、順接確定条件、ここは偶然的条件を表す。
参考
平安時代の貴族は、男も女も衣服に香(こう)をたきしめていた。「昔の人」は、橘の花の香りに似た香をたきしめていたのだろう。この歌以来、橘の花の香りは昔を思い出させるものとされた。
(『三省堂 全訳読解古語辞典〔第四版〕』「さつきまつ…」)

(たちばな 2016年5月 編集部撮影)
今回は、袖を詠んだ歌のうち、五月(今の6月頃)の橘の香りに関わる歌を取り上げました。『三省堂 全訳読解古語辞典』で「袖」を引くと、「橘の花の香りから昔の恋人の袖の香を思いおこすという叙情性豊かな歌であるが、「恋の部」ではなく、「夏の部」に収められている。選者の意識には「花橘」に重点が置かれていたのであろう。」と書かれています。
この「橘の香」がどんなイメージだったのか、『三省堂 全訳読解古語辞典』辞書で「たちばな」を引いてみると、以下のようなコラムがあります。
[読解のために]香りと生命力が賞賛された「橘」
時じくの香の木の実 橘の実は古くは「時(とき)じくの香(かく)の木の実(=季節を問わずいつも香ぐわしい木の実)」といった。大伴家持の「橘の歌」〈万葉・一八・四一一一〉によれば、「橘」は次のようなものだという。五月の初花の枝を娘たちへの贈り物にし、袖にしごいて香りを移し、果実は緒に通して腕輪とする。また、ほかの植物がかれる秋の時雨(しぐれ)、冬の霜雪(そうせつ)にもたえて、果実はいよいよ黄金の輝きを増し、葉も枯れない。
橘姓の由来 そのような季節を超えた生命力が賞賛されて、元明(げんめい)天皇は葛城王(かずらきのおおきみ)(=橘諸兄(もろえ))らに橘姓を賜ったという〈万葉・六・一〇〇九〉。
橘の花 平安京の内裏(だいり)にある紫宸殿(ししんでん)の右近(うこん)の橘は有名だが、個人の家の庭にも好んで植えられた。和歌用語の「花橘(はなたちばな)」は、初夏の季節感や懐旧の情を連想させ、ほととぎすと取り合わされる。