「城の崎にて」において語られる小動物のエピソードは,「死の前と後」から「死の直前」へ,そして「死の瞬間」というふうに,死の周辺から中心へと向かう順序に従って並べられていました。順に核心へと進む構造です。
そして,この順序に呼応して,語り手の描写態度や出来事の受け止め方に変化が生じます。今回と次回はその点について確認します。
最初のエピソードはハチの死についてです。語り手は,「足を腹の下にぴったりとつけ、触角はだらしなく顔へたれ下がって」いるハチの死骸を静かに眺めます(「冷たい瓦の上に一つ残った死骸を見る事は淋しかった。しかし、それは如何にも静かだった」)。そして,その静かさに親しみを覚えます(「忙(せわ)しく忙しく働いてばかりいた蜂が全く動く事がなくなったのだから静かである。自分はその静かさに親しみを感じた。」)
ここで語り手は,ハチの死に心が揺さぶられるわけではありません。このハチの死に遭遇する前から,語り手の「心には、何かしら死に対する親しみが起こって」いました。ハチの死骸を認めて一抹の淋しさを感じても,それを穏やかに受け入れるだけです。
語り手のそのような態度は語り方にも表れます。ことに以下の表現は特徴的です。
(90) a. 蜂は如何にも生きている物という感じを与えた。
b. それがまた如何にも死んだものという感じを与えるのだ。
c. それは見ていて、如何にも静かな感じを与えた。
(90)の3つの表現は,「蜂」や「それ」(ハチの死骸が横たわっている様子)が主体となって,語り手に対し一定の「感じ」を与えると述べています。語り手が受けた印象が授受行為の構図――与える人,受け取る人,そして受け渡される物が存在する――に当てはめられて表現されます。もっとも,この場合,受け取る人が語り手であることは明らかですが,テクスト上に明示されているわけではありません。
(90c)を例にとり,「静かな感じがした」という表現と比較してみましょう。「静かな感じがした」は,一定の認知の結果,どのような印象を持ったかを伝える表現で,結果のみに重点を置きます。こちらのほうが日本語としてはよくある表現です。
他方,(90c)は印象の出所(与える人)を明示し,他動的なはたらきかけがあったことを表します。そしてその結果,受け取る側にどのような印象が伝えられたかを示します。一定の印象を認識するにあたって,その原因と結果の関係をとらえるわけです。この点において,「静かな感じがした」に比べてより客観的で分析的な表現です。
留意すべきは,そういった分析的な表現が短い範囲のなかで3度も繰り返されることです。なかでも(90b, c)の「それ」はハチの死骸(がそのままになっていること)を指しています。物を主語とし,人を受け手とする他動詞構文は日本語においてあまり一般的ではありません。しかも,(90)の3つの表現のいずれもが「如何にも」という語句を含みます。つまり,あまり一般的ではない分析的な表現が,ことさら目立つように配置されているのです。ハチの死を見つめるときの落ち着いた客観的な印象は,こういった語り方にも起因しているのだと思います。
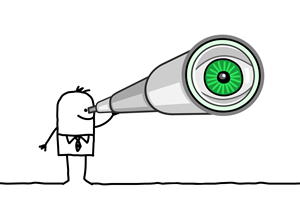
これに対し,ネズミの一件が語り手にもたらした衝撃は大きなものでした。ハチの死とは異なり,死に瀕するネズミの姿は語り手には他人事とは思えません(「今自分にあの鼠のような事が起こったら自分はどうするだろう」)。だから語り手は,「鼠の最期を見る気がしなかった」のです。
その語りは,ハチのときより臨場感を高めています。
(91) 鼠には首の所に7寸ばかりの魚串(さかなぐし)が刺し貫(とお)してあった。頭の上に三寸程、咽喉の下に三寸程それが出ている。鼠は石垣へ這上(はいあが)ろうとする。子供が二、三人、四十位の車夫が一人、それへ石を投げる。なかなか当らない。 (編集部注:ルビは実際には傍ルビ)
ここでは第一文を除き,非「タ」形の文末が続きます。ハチの描写においても非「タ」形の文末は見られますが,これほど連続することはありません。もっとも,非「タ」形が用いられたからといって,必ずしも現在進行形で出来事が繰広げられるというものではありません。ですが,ここでのように克明な描写が時間順に非「タ」形で繰り返されると,さすがに出来事が目の前で進行する印象を持たずにはいられません。ことに,最後の「なかなか当らない」は,語り手の視点が語りを行う現在時点から,過去の出来事の内部に入り込んだ印象をもたらします。他方,(90)のような他動詞の構文はここでは見当たりません。
「死の前後」を表していたハチの描写から「死の直前」を語るネズミの一節へと進むにつれて,つまり死の核心に近づくにしたがって,語り手の小動物に対する心理的な距離は近づくように思えます。
では,「死の瞬間」を表すイモリの描写はどのようになっているでしょうか。例によって,その話は次回になります。







