今年は2月が29日まである「閏年(うるうどし)」だ。この閏年は、旧暦の「閏月」、現代の「閏秒」と揃(そろ)えて表現するならば、「閏日」がある年となる。
「閏」という字は、「門」の中に「王」がいる、形が似ているが「壬」ではないと、子供のころ読んでいた学研の雑誌の付録に、王様の絵とともに書かれていたのを思い出す。『三省堂国語辞典』でもかつてその「 」を掲げていたことがあった【写真1】。現実にその字が使われることが少なくなかったことを反映したものと考えられる。JIS第2水準には、「王」が「玉」になった「閠」という異体字も収められている。
」を掲げていたことがあった【写真1】。現実にその字が使われることが少なくなかったことを反映したものと考えられる。JIS第2水準には、「王」が「玉」になった「閠」という異体字も収められている。
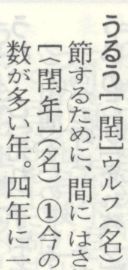
【写真1 三省堂国語辞典 第四版から】

【写真2 三省堂国語辞典 第六版から】
『説文解字(せつもんかいじ)』などに拠(よ)れば、古代中国では、太陰暦のために閏月が生じると、王は「門」中にいる習わしがあったのだという。日本での「うるう」は、その「閏」に「さんずい」が付いた「潤う」から付けられた訓と言われる。誤って付けられた訓だという説もあるが、「うるおう」という語義自体によって余るという意味になった、とも説かれる。
現在では、2月は閏年でなければ、そもそも28日までしかない。これは、中国ではなく西洋で定められた太陽暦によるもので、一か月の長さがまちまちとなっている。一か月の長さが31日に満たない月を「小(しょう)の月」と呼ぶ。
子供のころ、それがいつなのかについて、兄から「にしむくさむらい」と覚えるんだ、と教わった。流布している記憶法のようだ。2(に)月、4(し)月、6(む)月、9(く)月までは語呂合わせですぐに理解できたが、「さむらい」は「?」となる。11を漢数字で書けば「十一」で、それを縦にくっつけると「士」だと聞いて、「ああぁ」と感心した。しかし、特に漢字が得意ではなかった子供のころ、「さむらい? あれ、そうだったかな、でも「武士」ともいうから……、なるほど」と何とか理解できたが、「侍」という字もあるためか解せない思いが残った。
「士」という漢字を「さむらい」と訓読みすること自体は、「侍」よりは遅れるが中世より行われてきたことであった。意味も、「士」には「仕える者」(仕えるは「人偏」に「士」)や「専門の道芸を習得した者」といった意味があり、日本では「武士」の「士」や「士農工商」の「士」と、仕える相手も親王、公卿(くぎょう)などから、次第に武家である人びとへと変わっていった。発音も、「さぶら(候・侍)ふ」から、「さぶらひ」「さぶらい」、そして「さむらい」へと変化した語であった。
閏年よりもスケールの小さな「閏秒」は、テレビなどでもときどき話題とされる。それが必要とされる原因は、原子時計と地球の現実の自転との間で、時間に差が生じることだそうだ。
実は、地球の自転や公転というものも、不安定なところがあるのだそうだ。たとえばこの先の春分の日・秋分の日の日付については、「地球の運行状態は常に変化している」ために未確定だと国立天文台も述べている(//www.nao.ac.jp/QA/faq/a0301.html(*1))。当たり前のことだが、天体の運行の中に、私たちのすべての暮らしは置かれているわけであって、それは驚異であり、甚だしく神秘的である。宇宙空間での「王」も「士」も関係ない星々の劇的なダイナミズムを思い描く時間は、瑣事(さじ)に追われる日々だからこそ、持っていたいものだ。


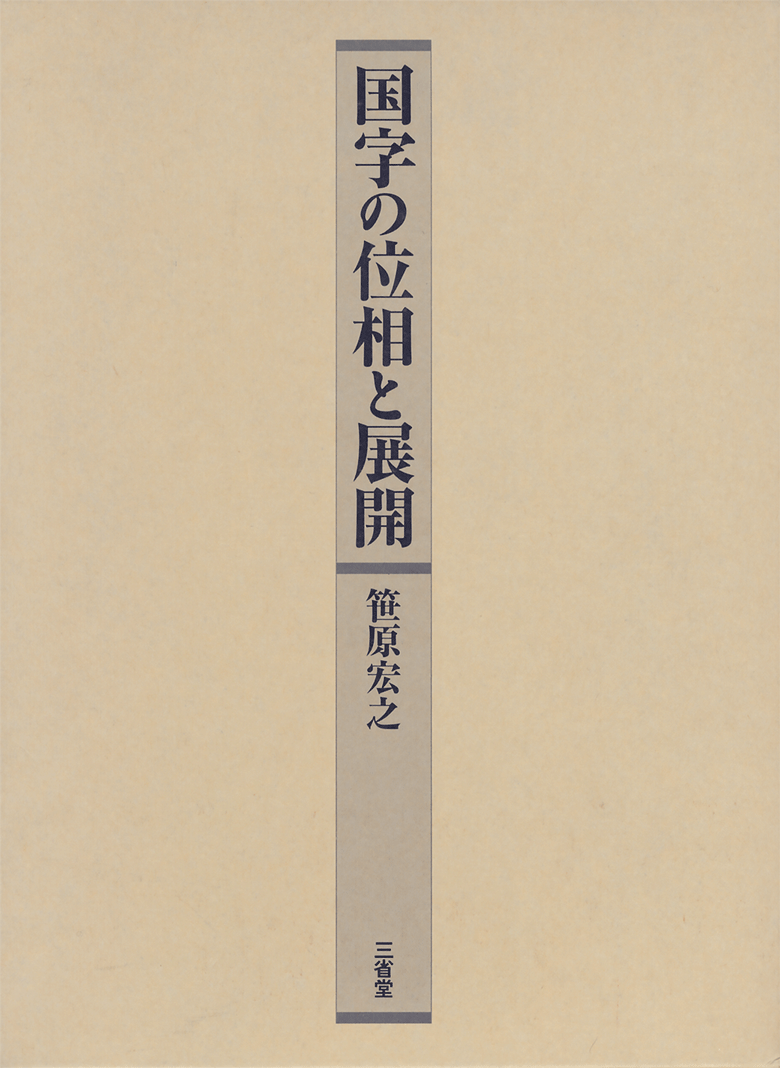
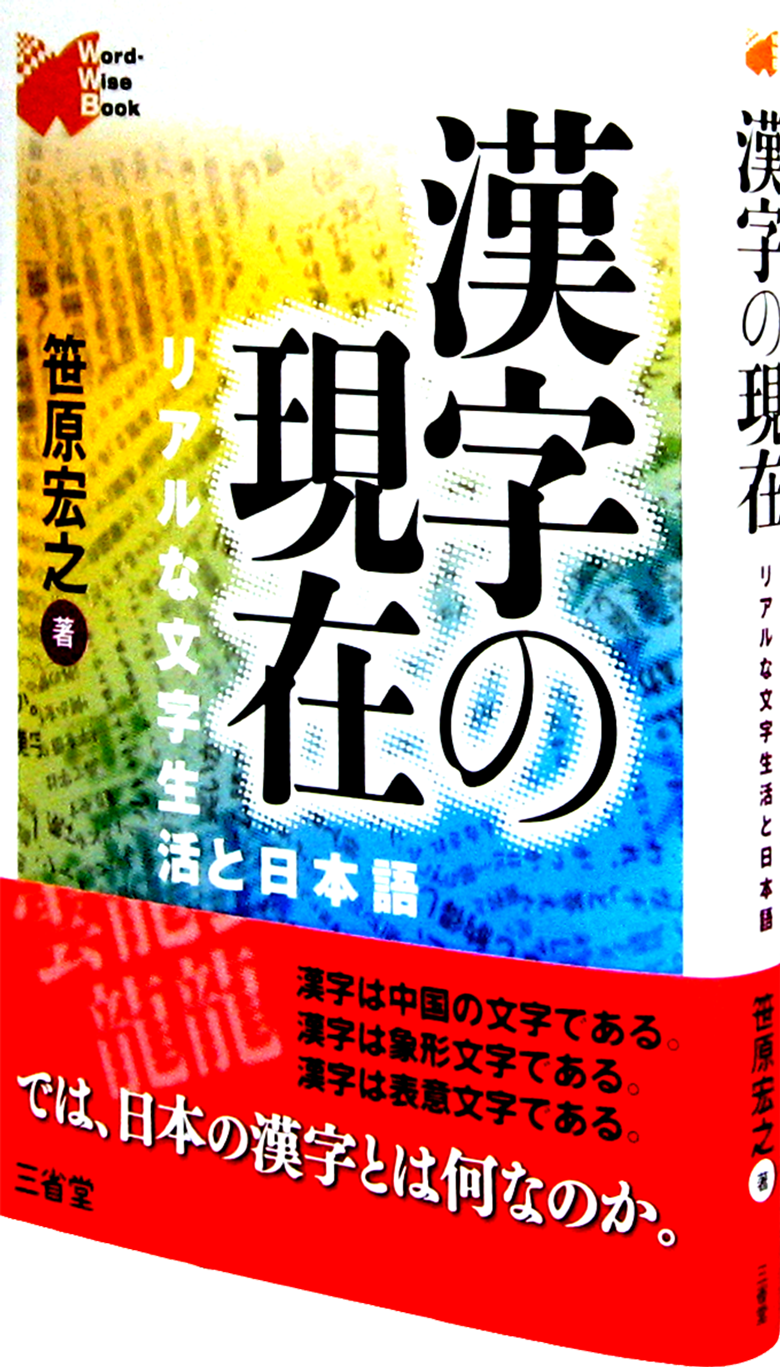




【注】