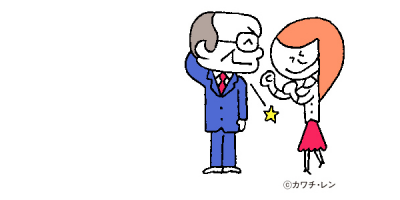「Underwood Typewriter No.1」と「Underwood Typewriter No.2」の成功は、ワーグナーに新たな悩みをもたらしました。特許にまつわる裁判の問題です。そもそも、ハーマンのビジブル・タイプライター特許(U.S. Patent No. 523698)はワトキンスに売却したものであり、「Underwood Typewriter」の売却益にかかるロイヤリティの支払いをめぐって、ワーグナー・タイプライター社とワトキンスとの間で、裁判を提起せざるを得なくなってしまったのです。ワーグナーは、法律扶助協会(Legal Aid Society)のフォン・ブリーゼン(Arthur von Briesen)に、弁護を依頼しました。フォン・ブリーゼンはドイツ系移民の弁護士で、フォン・ブリーゼンが協会長を務める法律扶助協会も、元々は、ニューヨーク在住のドイツ系移民のための弁護士組織として発足したものでした。
ワトキンスとの裁判に加え、ワーグナー・タイプライター社は、ウィックオフ・シーマンズ&ベネディクト社に訴えられます。「Underwood Typewriter」の印字機構が、ウィックオフ・シーマンズ&ベネディクト社の保有する特許(U.S. Patent No. 466947)に抵触している、というのが訴えの理由でした。この裁判は、アメリカン・ライティング・マシン社を巻き込んで、複数の特許に関する泥沼の裁判へと進展していきました。もちろん、ワーグナーとアンダーウッドは、この裁判の意図が、はっきりと分かっていました。ユニオン・タイプライター社の傘下に入らないタイプライター会社は、ことごとく潰してやろう、というのが、ウィックオフ・シーマンズ&ベネディクト社の意図するところだったのです。
1899年12月15日、ニューヨーク南部地方巡回裁判所において、ワーグナー・タイプライター社の代理人フォン・ブリーゼンは、ワーグナーやアンダーウッドの意を受けて、途方もない弁論を繰り出しました。この裁判の原告は、ウィックオフ・シーマンズ&ベネディクト社になっているが、それがそもそも変なのだ、というのです。なぜなら、ウィックオフ・シーマンズ&ベネディクト社の株式も特許も、全てユニオン・タイプライター社の支配下にあるのだから、原告は当然ユニオン・タイプライター社のはずなのだ、と。フォン・ブリーゼンは、さらに、ウィックオフ・シーマンズ&ベネディクト社の社長ベネディクト(Henry Harper Benedict)に対して、以下の質問をおこないました。
1892年の秋、あなたとファウラー(Charles Newell Fowler)氏との間で交わされた契約書の中に、次の文章が含まれていなかったかどうか証言していただきたい。「各社は、タイプライターにまつわる、属する、あるいは関わる、各社保有の全特許および特許による全権益を、この契約書が正式なものとなったあかつきには、譲渡及び委譲することを、ここに証し契約し同意する」
(フランツ・クサファー・ワーグナー(11)に続く)