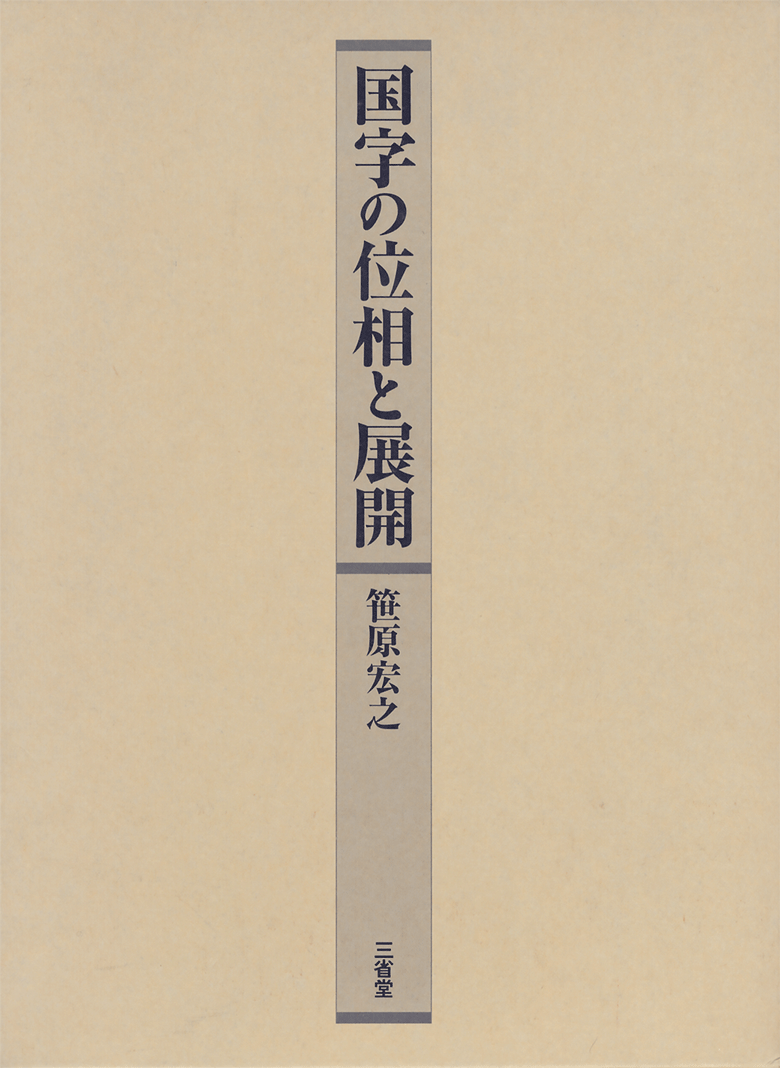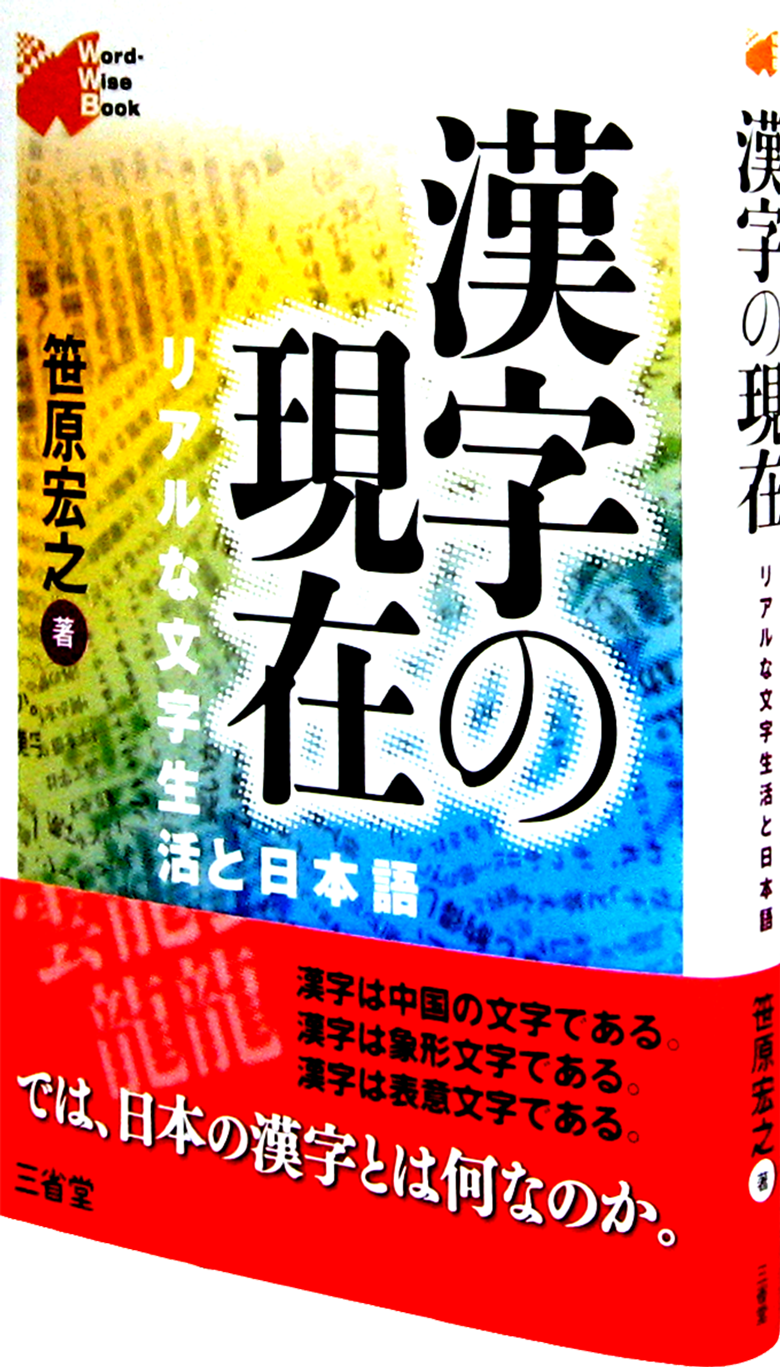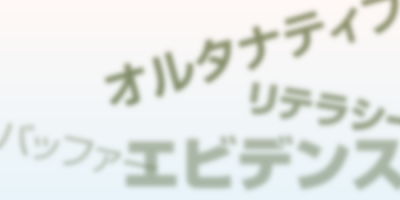大学に移って4年目にして、やっと研究室でお茶を淹れられるようになった。
慌ただしい日々であることに変わりはないが、散らかった研究室でも訪ねにいらして下さる方々が少しずつ増えてきたのと、お土産に東アジア各地のお茶を頂くことが増えたためだ。今話題のメラミンなるものも、これには関わらないだろう。

「茶」が中国で生まれた飲料であることは有名だ。元は「荼」(ト・ダ)という、ニガナなどを指す形声文字が転用されていたものとされる。なお、この字を「荼毘(ダビ)」と用いるのは梵語に音訳しただけのもので、茶とは関連がない。
その「荼」の「余」の部分を「人」の下の「一」を取り除いて「ホ」のように変えて「茶」とすることで、元の字との発音と意味の差を示したと言われている。下部の字体は「ホ」か「木」かなど、どのように書かれるか議論されることもあるが、これはそもそもそのようにして唐代に起こった俗字だという。この造字法は、伝統的な「六書」(りくしょ)では説明しづらい方法であり、「会意」の反対で、かつて「削意」などと呼ばれたような方法なのであろう。
「茶」は、中国でも各地で飲まれており、さまざまな種類が派生している。そして各地で方言による発音が生じている。例えば、茶を飲むことを、
広東や香港などの広東語では「飲茶」で「yam cha ヤムチャー」
北京を中心とする普通話では「喝茶」で「he1cha2 ホーチャー」
上海周辺の上海語では「吃茶」(喫茶)で「chi’zo チェッゾー」
などと言うそうだ。飲むことを意味する動詞がいっそう見事にバラバラになっているが、広東語は、日本語と同じく中国語の古態である漢文のような表現を残している。さらに、
福建や台湾などで行われる福建語では「啉茶」で「lim te リムテー」
とも言う。この1字目は、中国の歴代の辞書には、飲み終わる、貪るといった意味しか示されていないものであった。この方言ではあるいは「食茶」とも称するのは、茶を食していた古い習慣に対する古風な表現が残ったものかもしれない。
時代とともに中国の中原の地や福建、広東辺りから世界中に茶は伝わった。先の福建語の「茶」(te)が東南アジアから欧米などへと伝わっていったものと考えられている。インドや中東、アフリカなどを含めたいていの国では、茶を「チャイ」などと呼び、中国方言の原音の面影を伝えている。
日本では、かつて紅茶と緑茶をブレンドしたものだったか、「茶(チャ)ティー」という飲料が発売されたことがあった。そのCMをテレビで見て、私はある種の感慨を抱いた。中国から日本へ入ってきた「茶」という漢語が「チャ」である。一方、中国の福建省など南方から南洋、西洋へと渡り、ヨーロッパ各地で定着した発音が「テー」の類である。英語ではそれが「tea」と綴られ、発音の変化の流れの中で「ティー」へと語形を変え、ついに英米から日本へ流れ込んだ外来語として「ティー」となった。
つまりその両者が奇しくも東海の小島において結合したのが、この商品の名前だったのである。また、ペットボトルの「爽健美茶」を「そうけんびティー」と呼ぶ女子学生も現れた。もしかすると「茶」と「ティー」との間に、意味と発音の共通性が感じ取られているのかもしれない。兄弟同士のような関係の語が、長い旅の果てに日本で再会したことに、運命的なものさえも感じられまいか。
東アジアでは、茶は漢字・漢語とともに各地に伝来している。日本において「喫茶」「茶道」の語では「サ」と読むが(「チャ」とも読む)、これは唐音であり、「ジャ(ヂヤ)」「ダ」「タ」が伝統的な字音である。「チャ」というのは慣用音とされ、新しく中国から伝わった字音によるもののようだ。
韓国でも、喫茶店を意味する「茶房(タバン)」はすでに「年寄りじみた」語感を持つ語となり、外来語に取って代わられたそうだが、このように「茶」は「タ」と読まれるほかに、「チャ」という字音も使われている。「五味子茶(オミジャチャ)」は、5つの味を同時に楽しめる珍しい逸品である。無論、それに対する表記はハングルが主流となり、ここでも漢字表記は北朝鮮に続き、次第に韓国の人々からは縁遠いものとなっているようだ。
ベトナムでは、「trà」(チャー)がベトナム漢字音だが、「chè」(チェー)もよく使うようだ。後者は漢字音ではないが、やはり中国のいずれかの地方から伝わった発音が漢越語として残ったものではなかろうか。
ペットボトル入りの冷たいお茶も目を覚ますにはよいが、熱いお茶から湯気の立ち上る瞬間は、窮屈な日常を一瞬でも忘れさせてくれる。各地のお茶を口にすれば、居ながらにして彼の地へと、気持ちだけでも移すことができるかもしれない。