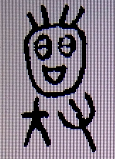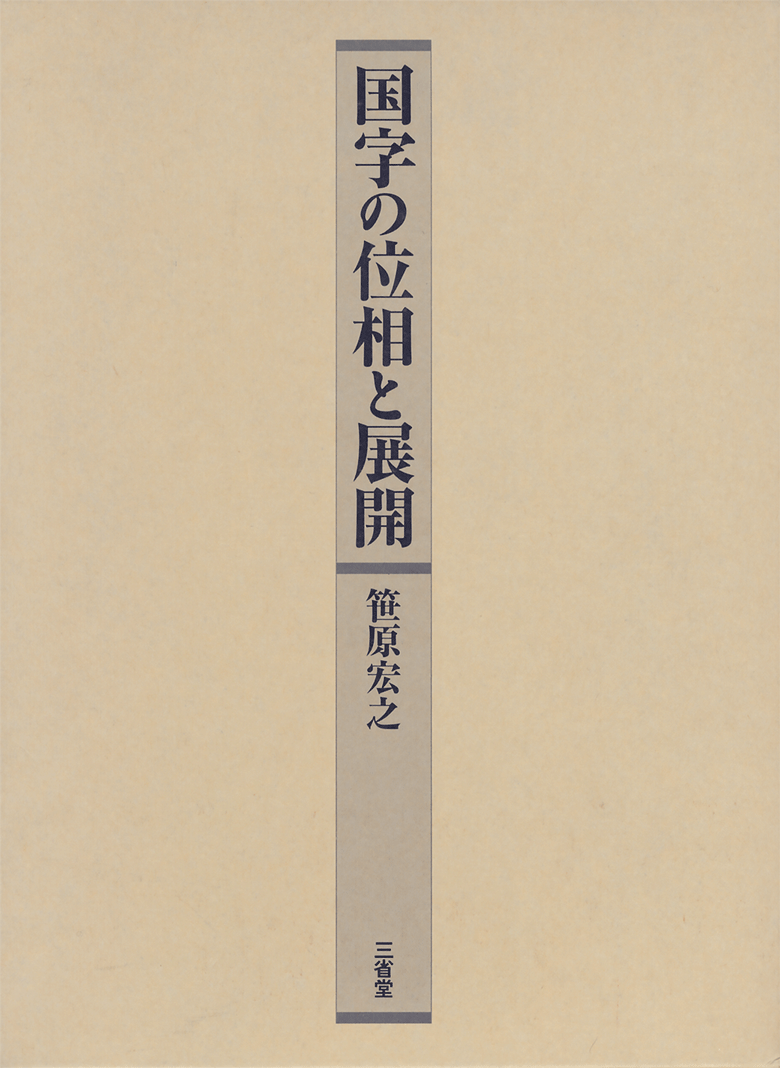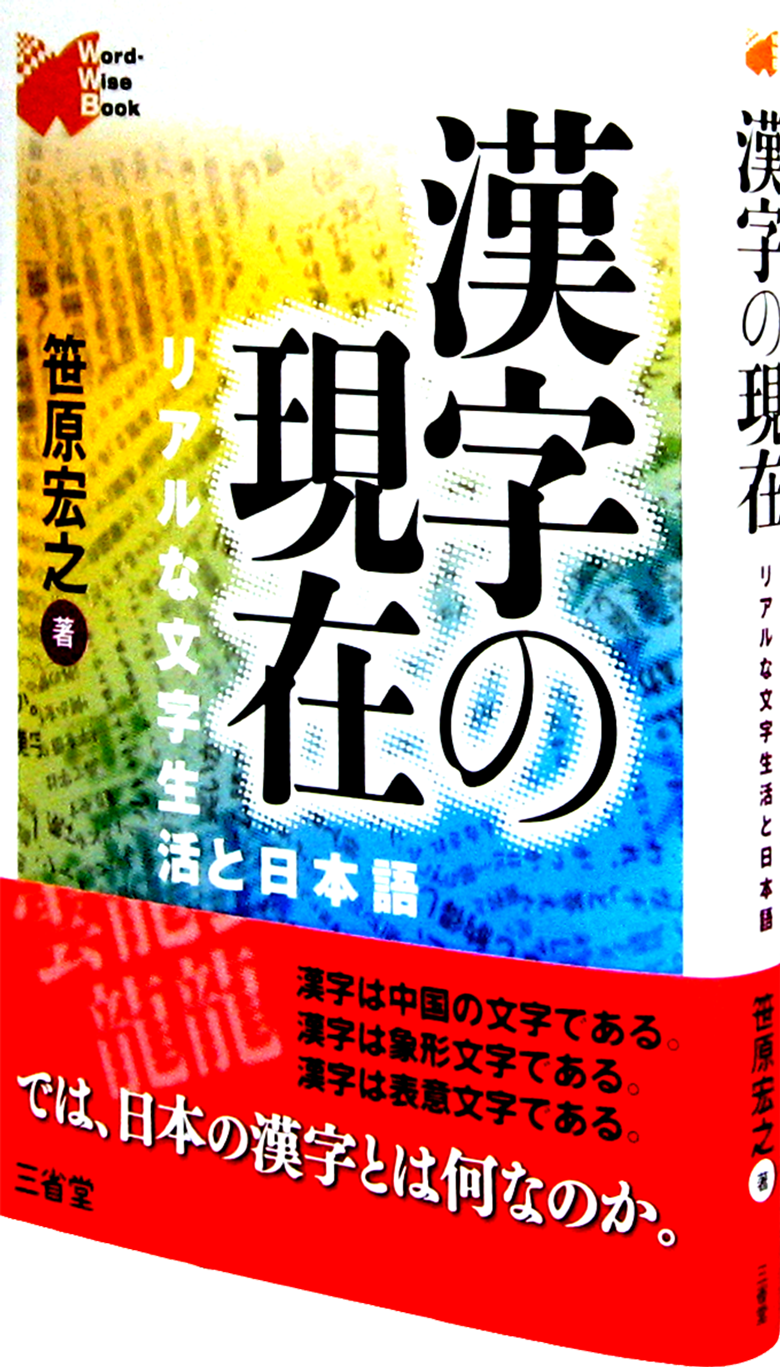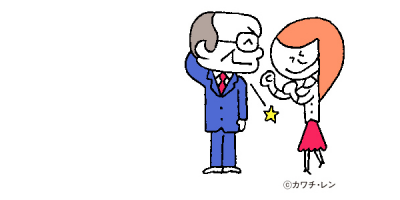辰年が明けて、巳年がやってきた。十二支を大学生たちに書いてもらうと、ミ年は「己」「已」「巳」「巴」「氾の右」など、混乱している様がうかがえる。

名前が「巳」で終わる男子学生は、電話で、ミはヘビのミです、と言ったところ、郵便物には「○蛇」と書かれて届いたそうだ。人名では、形が似た別の字の「己」をミと読ませることがあるほか、社名でも「已」をミと読ませるものがある。散歩中は飼い犬を怖がったという冒険家の植村直己氏は、1941年(巳年)生まれなので戸籍では名前の2字目は「巳」だとお話しになっていたそうだ。しかし、実際の戸籍では手書きで「己」のようだが、少し「已」に近い微妙な形だったとの報道があった(「朝日新聞」1985.2.3)。「おのれ」のほうが格好いいからと学生時代から「己」に変えている、とも話されていたそうだ。
江戸時代のころには、連載の第26回にも触れたとおりこれらは一般に混同を呈しており、区別するための口ずさみまで作られていたほどだ。ただ、金文でもすでに「巳」は「やむ」としても使われていたそうなので、漢字は一概にああであるべきだ、などと即断しがたいところがある。
十二支の漢字は、そもそもなぜタツを「辰」、ヘビを「巳」などと書くのか、いまだに定説がないようだ。互いに脈絡が感じにくいために、皆よく間違える。「み(どし)」を「未」と書いてしまった人もいた。かつて、漢民族とは異なる民族のことばに、音訳した漢字を当てはめたものという説も魅力的だが、なおも決定的ではない。それらの字をきちんと常用漢字表に加えることも検討されたのだが、十干は入れなくていいのかという議論が加わり、そこで認められた字や音訓は結局少ないままとなっている。日本では十二支は、漢文や世界史などでおなじみの十干よりも、一層生活に根ざしており、多くの年賀状はもちろん、生まれ年を表すのにも使われ、そして古文の日時や方位などの読解に不可欠なものである。ベトナムでは兎の代わりに猫が入っている、牛が水牛になっているなど、昔話のような話題も多い。
巳年は、私事ながら年男となる。次の年男はもう還暦だと思うと、時の流れが実感を上回り始めて久しいことに改めて気づく。辰年のうちにやっておきたいことがいくつもあった。その一つが「辰年」らしく「龍」(竜)の字に、おかしな古い字が2つあるということの紹介だった。周代のものとされる金文には、蝦が小踊りして喜ぶ挿絵のような象形文字、唖然としつつとぼけた表情でたたずむ漫画のような象形文字もあって、その真贋とともに興味を引く。後者については古い文献などからさんざん調べたのだが(下図はそれが後代に転写された1例)、こうして年を越し、まとめてどこかに書くのはこれからとなった。