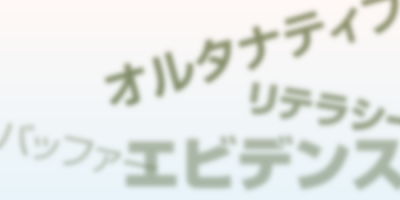私が初めて自分の国語辞典を買ったのは、中学1年の秋のことでした。『旺文社国語辞典』がそれです。
間の悪いことには、その翌年(1981年)に「常用漢字表」が告示され、たとえば「螢」は「蛍」と書くことになりました。せっかく買った国語辞典がとたんに古くなってしまいました。私は、やむをえず新版の辞書を買い直しましたが、それもまた『旺文社』でした。
ずっと父の実用辞典を使っていた私が『旺文社』の愛用者になったのには、その年ごろならではの理由がありました。

中学入学を境に、私の読書欲は爆発的に高まりました。子ども向けの前向きで健全な文学作品以外に、世の中には、後ろ向きで、不健全で、皮肉で、非常識な文学作品の多いことを知り、のめりこんでいきました。もっとも、主に読んでいたのは星新一、北杜夫、遠藤周作、そして夏目漱石といった人々の作品で、さほど過激なものではありません。
そうした一般の文学作品には、当然のことながら、国語の教科書に見られない表記やことば遣いがたくさん出てきます。
なかでも驚いたのは、丸谷才一さんのように、旧仮名遣い(歴史的仮名遣い)で文章を書く人がいたことです。私たちなら「三時間くらい飲んだんじゃないか」と書くところを、〈三時間くらゐ飲んだんぢやないか〉(『横しぐれ』)と書くのです。
戦前までは「思う」を「思ふ」、「いる」を「ゐる」と書いたということは、国語の時間に習いましたが、その方式を現代の文章に及ぼすのは新鮮でした。何より、「現代仮名遣い」「常用漢字表」という公のルールに真っ向から逆らう姿勢が痛快でした。
自分も旧仮名遣いを覚えたい――と、中学生の私は思いました。そして、実際に、担任の先生に提出する毎日の生活記録を旧仮名で書くようになりました。
〈本を読んでゐたらむづかしい横文字がでて来たので辞書でひいたら……〉
といった具合です。旧仮名遣いは実用辞典には載っていないため、どうしても国語辞典が必要になります。つまり、かなり特殊なケースかもしれませんが、私が『旺文社』を選んだ理由には、正確な旧仮名遣いを知るためということがありました。
国語辞典での旧仮名遣いの扱い方
旧仮名遣いの扱い方は、辞書によって異なります。今述べたように、実用辞典では旧仮名をいちいち書き添えることはしません。学習用の国語辞典も同じです。
これは、現代では、旧仮名遣いが目に触れることはあっても、自分で書くことはまずないという理由によるのでしょう。「思ふ」という表記を目にしても、それを「オモウ」と読めなければ、そもそも国語辞典は引けないし、また、読める以上は、「おもう」の項目を引けばいいので、辞書に旧仮名を添える意味はなくなります。
ただ、今の人でも、旧仮名遣いで書くことは皆無ではありません。たとえば、短歌や俳句をたしなむ人はおおぜいいます。短歌も俳句も旧仮名で書くものです。国語辞典の多くは、こうした特別の場合に備えて、旧仮名を示しているわけです。
ここでさらに、国語辞典の対応は二手に分かれます。
- 「思う」に「おもふ」と旧仮名を添え、「思考」には何も添えない。
- 「思う」に「おもふ」と旧仮名を添え、「思考」にも「しかう」と旧仮名を添える。
1と2の違いは、和語だけに旧仮名を添えるか、それとも、和語と漢語の両方に旧仮名を添えるかという違いです。
「思う」「舞う」「病(やまい)」などのことばは、古来の日本の固有語で、和語と言います。一方、「思考」「舞踏」「病気」などのことばは、古く中国から伝わった漢字を音読みするもので、漢語と言います。
このうち、短歌や俳句で仮名を交ぜて書くのはもっぱら和語のほうです。「思ひつつ」「舞ひにけり」「やまひの床」などと書きます。一方、漢語のほうは、仮名で書けば「しかう」「ぶたふ」「びやうき」となりますが、ふつうは漢字に隠れて表に出てきません。
そこで、同じ旧仮名遣いでも、和語の場合だけ示しておけば十分だと考える国語辞典と、いや、ほとんど必要はなくても、漢語の仮名遣い(字音仮名遣い)も添えておこうと考える国語辞典が出てきます。後者のひとつが『旺文社』でした。「旧仮名遣いを極める」という特殊かもしれない目的を持っていた私にとっては、頼りになる参考書でした。
もっとも、中学生のころの私が『旺文社』を選んだのは、仮名遣いだけが理由ではありませんでした。むしろ、もうひとつの理由のほうが大きかったかもしれません。