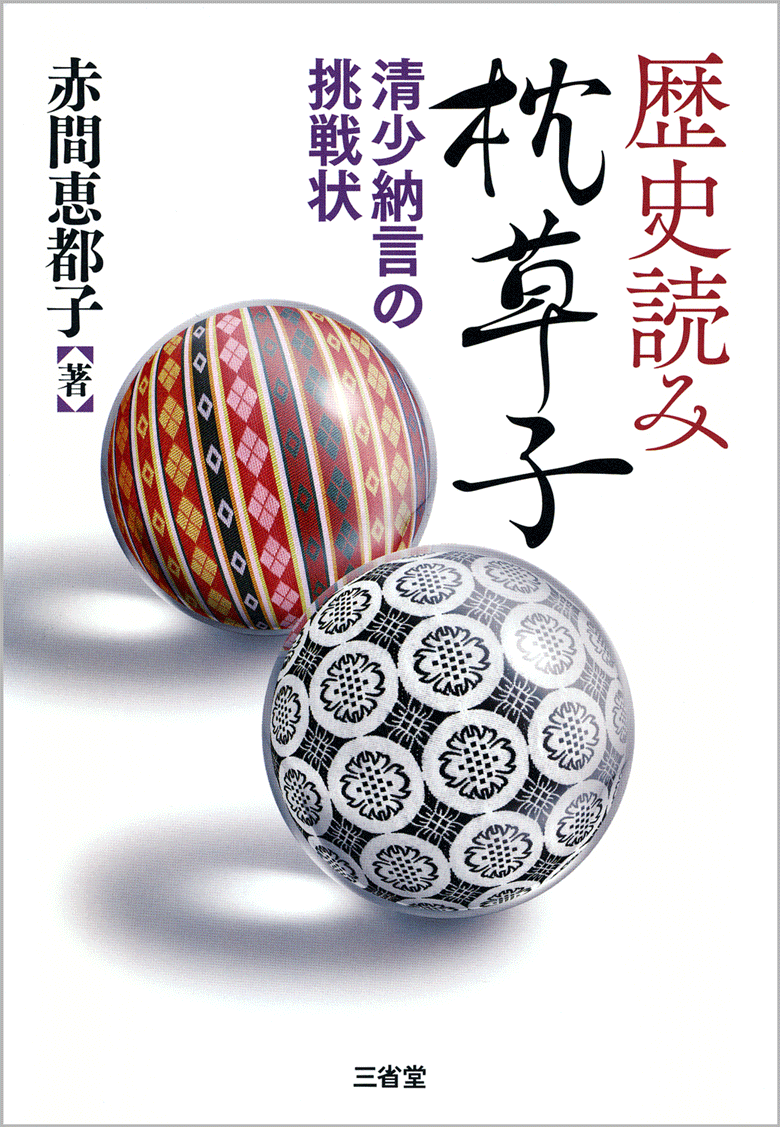前々回までお話していた藤原斉信について、もう一度、歴史的背景から触れておきましょう。斉信が定子サロンに出入りしていたのは、蔵人頭として天皇の身近に仕え、頭中将と呼ばれていた時期です。昇進して参議になると宰相中将と呼ばれ、国政の中核に参入することになります。斉信の参議就任は長徳2年4月24日、長徳の変の当日でした。
長徳の変の経緯については前回お話ししましたが、同日の斉信昇進は、斉信が長徳の変に絡む何らかの働きをして認められたことを暗示しています。長徳の変の発端は、花山院と伊周が通っていた女性たちの邸で起きた事件で、二人の恋愛相手はどちらも為光の娘、すなわち斉信の姉妹でした。事件現場を目撃し、表沙汰にしたのは斉信だったのかもしれません。いずれにせよ、長徳の変で参議に昇進した日を境に、斉信が完全に道長方についたことは間違いないでしょう。『枕草子』は、斉信の参議昇進をどのように描いているのでしょうか。
先に取り上げた「故殿の御服のころ」の段の逸話は、4月初め頃から7月の七夕にかけての清少納言と斉信の交渉を扱っていましたが、話の途中で斉信が宰相に昇進しています。しかし、この章段を4月24日に斉信が参議に就任した長徳2年のこととするのは、長徳の変前後の歴史的背景に照らし合わせて無理があります。伊周・隆家の配流、定子の落飾、二条邸焼亡と、中関白家に不幸な事件が立て続けに起きた時期に、清少納言が道長方の斉信と風雅な交流を持ったとはとても考えられないからです。したがって、この章段の出来事は、一年前の長徳元年のことと見る方が穏当なのですが、その場合、斉信の昇進時期が歴史的事実と食い違うという問題が出てきます。作者の記憶違いだという説もあります。しかし主家凋落の日を清少納言が忘れるはずはないと思います。
作者は事実を曲げて、『枕草子』に斉信昇進のことを記したのです。それはなぜなのでしょうか。
この段には、他に、清少納言が斉信の参議昇進を保留するよう、一条天皇に直訴している記事もあります。当時、女房たちの進言が男性貴族の人事を左右することもあったようですが、斉信昇進は長徳の変に関わる政治的処遇によるもので、女房風情の口出しできる範中にはありません。そんなことは百も承知で、斉信の朗詠はとても素晴らしいから、もうしばらく宰相にならないで天皇にお仕えしたらいいのに、と訴える清少納言。それを受けて、一条天皇が大笑いし、「さなむ言ふとて、なさじかし(そのように言うから、参議にするまいよ)」と答えます。この後、「されど、なりたまひにしかば、まことにさうざうしかりしに(それなのに、参議に就任なさってしまったので、本当にさびしかったところ)…」と記事が続いていくのですが、作者は、よほど斉信の昇進にこだわっていたに違いありません。
定子を追い詰めた長徳の変の状況を描写することはできなかったけれど、中関白家没落を足がかりに昇進する斉信の事を作者は記さずにいられなかったのだと思います。
長徳2年2月に定子が内裏を退出した時、宮中に居残っていた清少納言を訪問した斉信の華やかな姿を、作者は最後まで詳細に描ききっています。そこで物語の主人公のようだと評価した斉信を、後に定子に報告し称讃する清少納言は、一方で、斉信との交際に一線を設け、定子不在の宮中で彼と個人的に応対することを避けています。『枕草子』に取り上げられた斉信の宰相昇進は、作者が定子サロン女房としての矜持(きょうじ)を保ちつつ示した、斉信との決別の意志表示だったのだと思います。