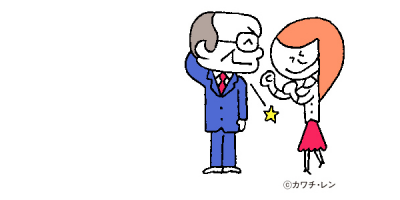「百学連環」の「総論」、その目次を眺めているところでした。目次といえども、じっくり見てみると、いろいろなことを考えさせられます。いきなり本文にとりかかるのもよいけれど、ここでは先にこれから歩き回る土地の地図をざっと眺めておこうという目論見で、この目次を見ているのでした。
さて、今回は残る二つの項目「新致知学」「真理」のうち、前者を見ることにしましょう。
まず「新致知学」とは、この言葉自体、いまでは見慣れないものです。「新」とついていることから、なにか新しいものだということは推察されます。「新しい致知学」ということでしょうか。「致知学」は「学」の字から、私たちにもお馴染みの「~学」という学術領域の一種であることが窺えますね。では、いったいこれはどんな学術なのか。
「致知」という字を訓読みすれば、「知に致る」となるでしょうか。「知に致りつくための新しい学」とはこれいかに。なんだか期待が湧いてくる名称です。では、その下に置かれている小見出しはどうか。こうなっています。
Jhon Stuart Mill
帰納法 Induction 演繹法 Deduction
この二つだけです。前者は、19世紀イギリスの哲学者ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の名前です。西周(1829-1897)は、ちょうどJ.S.ミル(お父さんがジェームズ・ミルという名前なので、紛れないようにこう記します)の20年後に生まれ、没していますので、同時代人と言ってもよいでしょう。
J.S.ミルも幅広い領域でものを考えた人でしたが、その主な著作を見ると、先ほどの「新致知学」の正体が見えてきそうです。そのOn Liberty(1859)が『自由之理』として日本に初めて訳出紹介(訳者は中村正道)されたのは、1872年のこと。ちょうど「百学連環」講義が行われた時期でもあります。そのJ.S.ミルの著作は大きく分けると、論理学、政治学、経済学を扱ったものです(その知的経歴を描いた『自伝』も忘れがたい書物でした)。
しかも、二つ目の小見出しには「帰納法」と「演繹法」という、いまでも私たちがお世話になっている言葉が見えています。これは、現在ではもっぱら数学や自然科学の分野で教えられる論理の方法です。
つまり、「新致知学」とは論理学のことなのでした。ですから、おそらくこの訳語の元となった語は、Logicだと思われます。しかし、なぜ西先生はこれを「新致知学」と訳したのか。ここで論理学の歴史が念頭に浮かぶ人は、あるいはピンとくるものがあるかもしれません。なぜ「新」なのか。そして、なぜそれは「知に致る学」なのか。西先生は、なぜInductionとDeductionを「帰納」「演繹」と訳したのか。というか、この二つの漢語は、そもそもどういう含意があるのか。
本文を見ていないので、疑問が疑問を呼びますが、このように読書を開始するにあたって、いくつかの疑問を思い浮かべるということもまた、読書を豊かにするための食前酒のようなものなのです。物語の冒頭で謎が提示される探偵小説を連想してもよいでしょう。「犯人は誰だろう?」「どうしてこうなったんだろう?」という疑問に惹かれて、ページを繰るのを止められず、気づいたら朝まで読んでいたということがあります(筆者は先日も、新訳が出たジョン・ディクスン・カーの『帽子収集狂事件』〔三角和代訳、創元推理文庫〕をそんなふうにして読んでしまいました)。
それはなにも探偵小説やミステリだけに限りません。こうした文書を読む場合にも、文書に肉薄するための大切な動機付けを与えてくれると思います。というわけで、次回は「真理」の項目を眺めてみることにしましょう。