日本で最初にベントン彫刻機を輸入したのは印刷局だった。印刷局では、官報や政府印刷物などを印刷しており、「印刷局型」ともいうべき独自の明朝書体をもっていた。また、日本の活版印刷術において科学的研究をおこなった工学者・矢野道也(1876-1946)が所属していたため、はやくからベントン彫刻機による彫刻母型に注目し、研究をすすめていたという。[注1]
ベントン彫刻機を輸入したのは明治45年(1912)のこと。亀井寅雄が印刷局でベントン彫刻機に出会う7年前のことだ。母型彫刻機の輸入については、『内閣印刷局七十年史』(内閣印刷局編纂、1943)にもしっかり記録されている。
其の後三十一年(筆者注:明治)十一月内閣官報局と併合してより、更に活字母型の改造に努む。三十六年二月ライノタイプを購入設備し欧文印刷の便を図る。又四十五年以来康熙字典の字体を基礎として活字字体の改造を企て、殿版康熙字典に依ることとし、同時に鋳造方法の改良をも計画し独逸及び米国より母型彫刻機四台を購入し(下線筆者)、煩雑なる旧式方法を廃しニッケルと銅との合成金に直接彫刻して母型を得、之に依りて鋳造するの方法に革め、大いに製造能率の増進を見たり。而して官報印刷に使用する活字の如きは、専ら此の方法に依りて鋳造したるものを用ふ。[注2]
印刷局はその後、大正5、6年(1916、7)ごろにポイント式活字の鋳造に着手した。9ポイント、8ポイント、12ポイントの新活字を次々完成させ、これらの活字は大正8年(1919)1月4日の『官報』から使用された。いずれも康熙字典の文字を写真によって縮写し、それを書体として母型をつくった印刷局独特のもので、
字画正確、字体鮮明なるのみならず、一種の風韻を持するの故を以て大いに識者の好評を得たり[注3]
と印刷局は記している。
ところが矢作勝美『明朝活字の美しさ』によれば、〈この書体は評判が悪く、その後廃棄されている〉とある。[注4] 長体がかった線の細い書体だったため、汎用性が低かったのか、結局はもとの明朝体に戻したようだ。そもそもが、印刷局ではベントン彫刻機は使いこなせず、地下室につて置かれたという話もある。[注5] だからこそ、亀井寅雄がこの機械に出会ったとき、印刷の専門家たちにもまだ知られていない存在だったのだろう。
それにしても、「門外不出の秘蔵の機械」であったベントン彫刻機が、なぜ明治末というはやい時期に印刷局に輸入されたのだろうか。
矢作勝美『明朝活字の美しさ』には、印刷局活版部長の小山初太郎が明治40年(1907)に欧米視察におもむき、ATFにてベントン母型彫刻機の実習を受けて帰国し、母型彫刻機の導入となった、とあるが、典拠がわからない。
亀井寅雄によると、
余談ながら印刷局がこの機械を持っている訳は、かつてサンフランシスコで日米博覧会があった時、ATF会社が印刷局に非常に厄介になったことがあり、その恩寵に酬ゆるため門外不出のこの機械を二台特別に渡した
とある。[注6]
印刷局が所有していたベントン彫刻機は1台だけなので、「2台」という数字が正しいとすれば、もう1台はどこにいったのか?
実は、三省堂より先に、東京築地活版製造所がベントン彫刻機を1台所有していた。入手年代には諸説あるようで、大正12年(1923)とする説もあるが、もし寅雄の「印刷局に2台渡した」という記述が正しければ、このうちの1台がなんらかの理由で東京築地活版製造所にわたったとも考えられる。
今井直一も東京築地活版製造所について、〈たまたま印刷局にベントン母型彫刻機が輸入されるので、その機会に同機を1台手に入れることに成功したのであった〉〈同社がその後解散するまで、かなや数字を彫刻したのみで、明朝漢字には成功しなかったようである〉と書いている。[注1]
いずれにしても、印刷局が有していた、日本ではまだほとんど知られぬベントン彫刻機を、亀井寅雄は見つけた。そして、どうしても手に入れたいと考えたのだった。
[参考文献]
- 『昭和三十年十一月調製 三省堂歴史資料(二)』(三省堂、1955)から、
亀井寅雄「三省堂の印刷工場」
今井直一「我が社の活字」 - 『亀井寅雄追憶記』(故亀井寅雄追憶記編纂準備会、1956)
- 亀井寅雄 述/藤原楚水 筆録『三省堂を語る』(三省堂、1979)
- 『三省堂の百年』(三省堂、1982)
- 矢作勝美『明朝活字の美しさ』(創元社、2011)
- 佐藤敬之輔「活字に生きた人々〈下〉君塚樹石の仕事」『エディター』47号(1978年7月号、印刷:精興社)



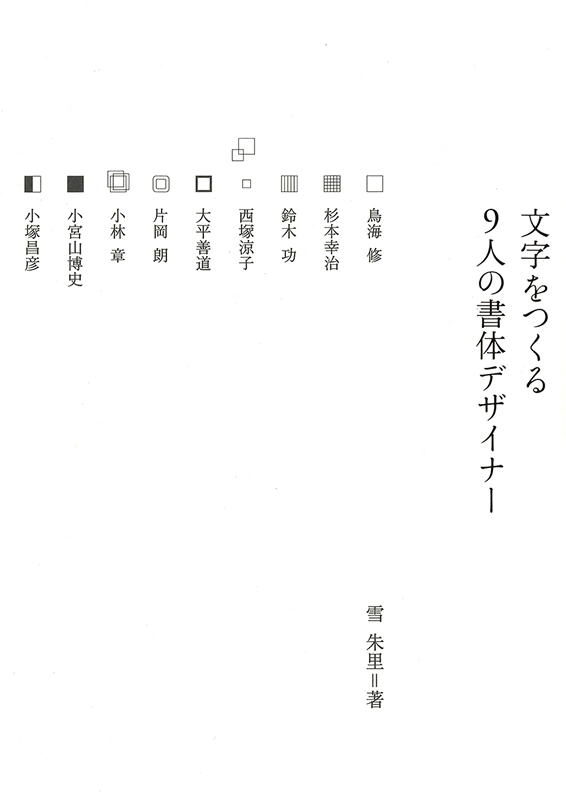


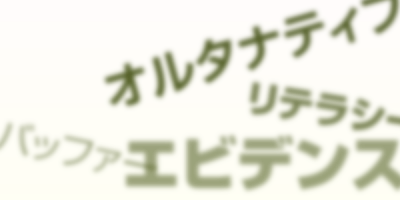

[注]