日本では明治末~大正にかけて、3社がアメリカン・タイプ・ファウンダース(ATF)製ベントン彫刻機をもちいていた。三省堂よりさきに印刷局と東京築地活版製造所が入手していたことは、連載第11回「ベントンとの出会い」、第12回「印刷局とベントン彫刻機」でふれたとおりだ。しかしその後の調査で、あらたに見えてきたことがある。前回、東京築地活版製造所(築地活版)がATFからベントン彫刻機を購入したのは大正10年(1921)だとのべた。同社のベントン彫刻機その後について、あらためて見ていきたい。
*
大正12年(1923)9月1日に関東地方をおそった大地震は、印刷界にも多大な被害をあたえた。印刷局のベントン彫刻機は、震災によって起きた大火事で工場ごと焼けてしまった(王子の抄紙部だけが焼失をまぬがれた。また、活字母型はぶじだった)。三省堂は本社と神田三崎河岸工場が全焼したものの、ベントン彫刻機は横浜の保税倉庫のなかにあったため、ぶじだった。では、東京築地活版製造所(築地活版)はどうだったのだろうか。
関東大震災が起きた直後に刊行された『印刷雑誌』大正12年10月号(印刷雑誌社、1923)は、震災号として、東京市内の印刷業者およびその関係者の被害程度や再興方針、現状などをつたえている。
この号に、築地活版の宮崎榮太郎が〈今度の災害は実に言語に絶している。我等の誇りであった美しき東京は自然の暴虐に依って極めて短時間に一たまりもなく蹂躙し尽されて終った。そして各方面に計り知られない大損失を与えた〉という出だしではじまる悲痛な報告をしている。記事タイトルは「活版界の一大損失 ――東京築地活版所の焼失――」。[注1]
宮崎は、〈活字がどれだけなくなり、字母がどれだけ焼け機械が幾台駄目になったかと言う様な具体的な報告を避けたい〉とし、明治6年(1873)の創業以来50年間にわたって日本文化に多大な貢献をしてきた同社が類焼という災厄にあったことは、物質上のみの損失におさまらない、と力説している。社長の野村宗十郎が熱心に集めた活字や活版に関するあらゆる文献や参考品も焼けてしまった。宮崎が日々研究し、仕事を通じて気づいたことを書きとめていたノートも、あと1、2年もしたらまとめようとかんがえていたのに、会社に置いてあった自分の本とともに灰となってしまった。〈之等の焼失は幾ら金を出しても得られないだけに惜みても惜み足らない〉〈私としては痛恨の極みである〉と、宮崎の悲しみは深い。[注2]
それもそのはず、築地活版は関東大震災の2カ月まえ、大正12年(1923)7月にあたらしく地下1階地上4階建ての本社工場(東京市京橋区築地)を建てたばかりだったのだ。
震災さえなくば、実にあの不幸さえなくば、築地二丁目の河岸に、鉄筋コンクリート四階建の、建坪一千坪に余る純白の建物が、聳え立つのであった。其主要なる建物百四十坪が功成って、正に事務所が移転するばかりになって、彼の大災害は降って湧いたのだ。
「輪奐の美を極めて 築地活版の新建築復活」『印刷雑誌』大正13年8月号[注3]
ATFから購入したベントン彫刻機も7月に新社屋にすえつけ、稼働を開始したところだった。[注4] そこに大地震がおそった。
同所は新築の四階建てを除くの外は全部煉瓦造りの事とて非常に危険に思われたが、最初の地震で一名の圧死者を出しただけで他は無事に避難したが其の後夜になって銀座から精養軒辺を焼いた火はついに同所にも延焼し付近一帯を火の海として社長野村氏の宅も間もなく全焼の厄に遭った。
「罹災同業者巡り」『印刷雑誌』大正12年10月号[注5]
何というても大問題は、会社事業の中心生命であった所の母型の焼失したことであった。されば社長は『少し遅くなっても決して本木翁以来の暖簾に疵をつけるな』と社員を警めて、焼残りの母型の整理をなすと共に、漢字母型の新調に取りかかったが、先頃米国鋳造会社(筆者注:ATF)から購入したベントンの母型彫刻機の焼失せる為め(下線筆者)其進捗は容易でなく、旧活字各号が愈よ一般の需要に応ぜられるに到るのは三月初めになるであろう。
「壮なるかな復興の気分」『印刷雑誌』大正13年1月号[注6]
築地活版は、築地にあった建物140坪の4階建て新本社工場と、月島にあった分工場をうしなった。なによりの問題は、活字だけでなく、母型までもが焼けてしまったことだった。母型さえあれば活字は鋳造できるが、母型がなくてはどうしようもない。急ぎ母型をつくろうにも、そんなときにたよりになるはずの、そして、ATFから購入してこれから本格稼働というところだったベントン彫刻機も焼失してしまったのだ。[注7]
先述した宮崎榮太郎の「活版界の一大損失」には、こう書かれている。
昨年の博覧会には審査総評に、母型が旧式な手工に依って製作せられ未だ彫刻機械が使用されないのが遺憾だと云われたのであったが、本春は世界一と折紙付のベントンエングレービングマシン(筆者注:ベントン彫刻機)が設備され、之に伴ってライツのMMメタルクロスコープが来て三千九百倍迄自由に拡大写真が撮れるので、地金の研究に非常な便利を得る様になったので、やれ嬉しやと思ったら灰燼に帰して終った。
宮崎榮太郎「活版界の一大損失 ――東京築地活版所の焼失――」『印刷雑誌』大正12年10月号[注8]
これからというときに見舞われた大震災で、宮崎のくやしさが伝わってくるようだ。
しかし、当時日本で最大の活字製造所であった築地活版は、みずからをすみやかに、かつ以前よりも立派に復興させることこそが活版界や日本文化のためとかんがえ、大阪出張所の母型を流用しながら(それだけでは活字鋳造の需要には追いつけなかったが)、すぐさま復興にむけて奔走した。
五十年前の明治六年に帰って創めて居ない。今日から出発して居るのである。
宮崎榮太郎「活版界の一大損失 ――東京築地活版所の焼失――」『印刷雑誌』大正12年10月号[注9]
――復興にむけての力強いことばだ。
そんな築地活版への追い風となったことがある。
同社は、焼けてしまったベントン彫刻機のほかにもう1台を、ATFに注文中だったのだ。
(つづく)
[参考文献]
- 宮崎榮太郎「活版界の一大損失 ――東京築地活版所の焼失――」『印刷雑誌』大正12年10月号(印刷雑誌社、1923)
- 「輪奐の美を極めて 築地活版の新建築復活」『印刷雑誌』大正13年8月号(印刷雑誌社、1924)
- 板倉雅宣『活版印刷発達史 東京築地活版製造所の果たした役割』(印刷朝陽会、2006)
- 「罹災同業者巡り」『印刷雑誌』大正12年10月号(印刷雑誌社、1923)
- 「壮なるかな復興の気分」『印刷雑誌』大正13年1月号(印刷雑誌社、1924)
- 「さすがは築地活版 至れり尽せる活字製造の設備」『印刷雑誌』大正15年10月号(印刷雑誌社、1926)
- 「印刷所の顧問 印刷材料・機械仕入案内」『印刷雑誌』昭和10年4月号(印刷雑誌社、1935)



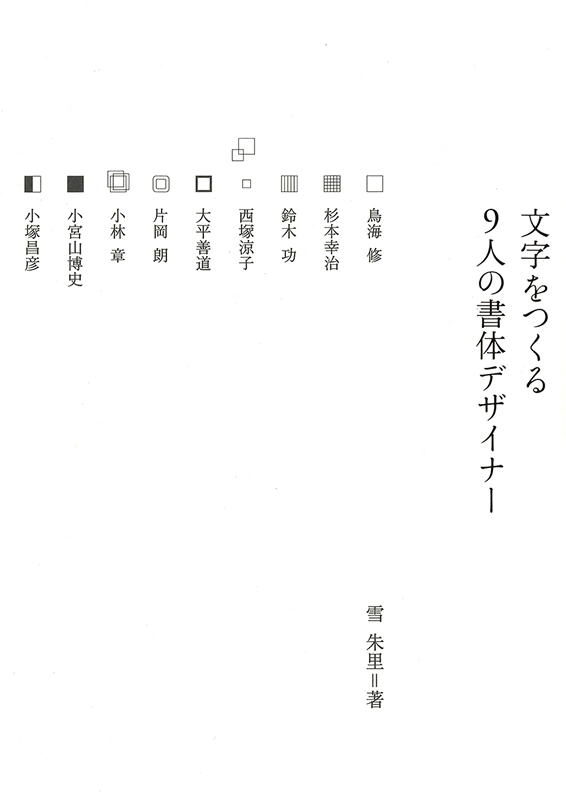




[注]
宮崎榮太郎「活版界の一大損失 ――東京築地活版所の焼失――」『印刷雑誌』大正12年10月号(印刷雑誌社、1923)P.9
「壮なるかな復興の気分」『印刷雑誌』大正13年1月号(印刷雑誌社、1924)P.17
「さすがは築地活版 至れり尽せる活字製造の設備」『印刷雑誌』大正15年10月号(印刷雑誌社、1926)P.10
「印刷所の顧問 印刷材料・機械仕入案内」『印刷雑誌』昭和10年4月号(印刷雑誌社、1935)P.23