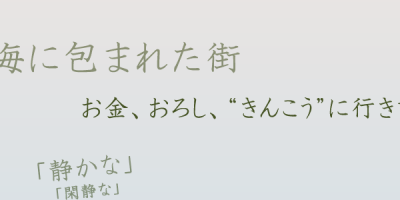この文章がアップされる頃、私は某国の某地方都市に出張しているはずだ。その地では男性はヒゲをはやしていないと子供扱いされるとか、その道の男性に狙われるとかおどかされて、半信半疑のまま、いま生まれて初めてヒゲを伸ばしている。知人に会うと「定延さんがヒゲですか」のようなことを言われ、自分でも「いや、実は海外出張で」と、あわてて事情を説明したりする。私は皆さんもご存じの通り、まじめな『堅物』キャラですから。セクシーだとか野生派だとか、そういうキャラクタになど変わりませんって。
友人どうしが結婚し、やがて出産報告が届く。めでたいことだが、彼らに、自分が知らない『男』と『女』の面があると思い知らされる瞬間でもある。あいつらが子作り、うーん想像したくない想像したくない。
このように私たちが日常しばしば感じる「あの人がねぇ」的なショックは、「相手に応じてスタイルを使い分ける」などという考えでは説明できない。たとえば、
「ねー、お昼なんにしゅる~?」
「んー、わかんないでしゅ~」
などという甘ったるい恋人会話を、何かの拍子に親兄弟知人たちに聞かれてしまった2人は、もうどうしようもないだろう。「えー皆さんに対しては、いつもそれなりのスタイルで接しておりますが、恋人に対しては、特に親しいスタイルで接しているというわけであります」と、スタイルの使い分けを主張して胸を張っても、恥の上塗りにしかならない。これが「スタイルの使い分け」の問題ではなく、「うわー、あの人、恋人相手だとあんな『幼児』キャラになっちゃうんだー」というキャラクタの問題であることを、私たちはよく知っている。
たしかに、「スタイルの使い分け」という考えが当てはまる場合もないわけではない。得意先の会社社長と自分の部下に、「あの件をよろしく」と依頼する場合どうするか。得意先の社長には「あの件どうかよろしくお願いいたします」と丁寧に言って頭を下げる。自分の部下には「あの件、君もよろしくな」などと軽く言って肩を叩く。得意先の社長に向かって丁寧に依頼する様子を部下に見られても別段恥じることはない。部下に向かってぞんざいに依頼するところを得意先の部長に見られてもどうということはない。ここでは話し手は、同じメッセージ[あの件をよろしく]を伝えるに際して、相手との人間関係に応じてスタイルを変えている。
だが、得意先の社長に対して「あッ、社長、いつもお世話になっておりますですぅ!あッ、あの件でございますけどォ、なにとぞ、えー、よろしくお願いいたします、[空気をすすって]シー」とネコナデ声で平身低頭してモミ手する一方で、自分の部下に対しては机の上に足を投げ出し「あれ、おめえ、気ィ抜くんじゃねーぞ、エーッ」とねめつける、という場合はどうか。得意先の社長に向けた言動は部下には見られたくないだろうし、逆に部下相手の言動は得意先の社長には見られたくないだろう。ここでは、単に「相手との人間関係に応じてスタイルを変えている」と言う以上の、「別人」かと思いたくなるような変化が起こっている。
といっても、この変化は、文字通り「別人」になってしまうほどの根本的なものではない。島尾敏雄の小説『帰巣者の憂鬱』には、夫婦喧嘩で初め「わたしが悪かった。行かないで下さい」などと言っていた妻が、やがて「アンマイ、ワンダカ、テレティタボレ」などと故郷の島ことばをしゃべりだし、我に返った後は「わたし何かして?」のように再び共通語でしゃべるという場面がある。島ことばをしゃべっていた間の記憶は、共通語に戻った時点で引き継がれず、消えてしまっている。上で述べた変化は、このような根本的な変化(仮に「人格」の変化と呼ぶ)とは異なり、言語も記憶も引き継がれている。
相手に応じて自在に変えてよいスタイルと違って、変わらないことが期待されているもの。それが変わってしまったところを目の当たりにすると、「うわ、こいつ、オレの前では猫かぶってたんだ」「この人、強い相手にはとことん弱いな」「あの人、恋人の前ではこんな3頭身になっちゃうんだ」などと、何事であるかすぐに察しがついてしまうが、見られた方も見た方も気まずいもの。かといって、「人格」ほど根本的ではないもの。前2回で述べてきた「かっこいい人」「まじめな人」「下品な人」のようなさまざまなキャラクタ(人物イメージ)は、この「スタイル以上、人格未満」のレベルに群生している。